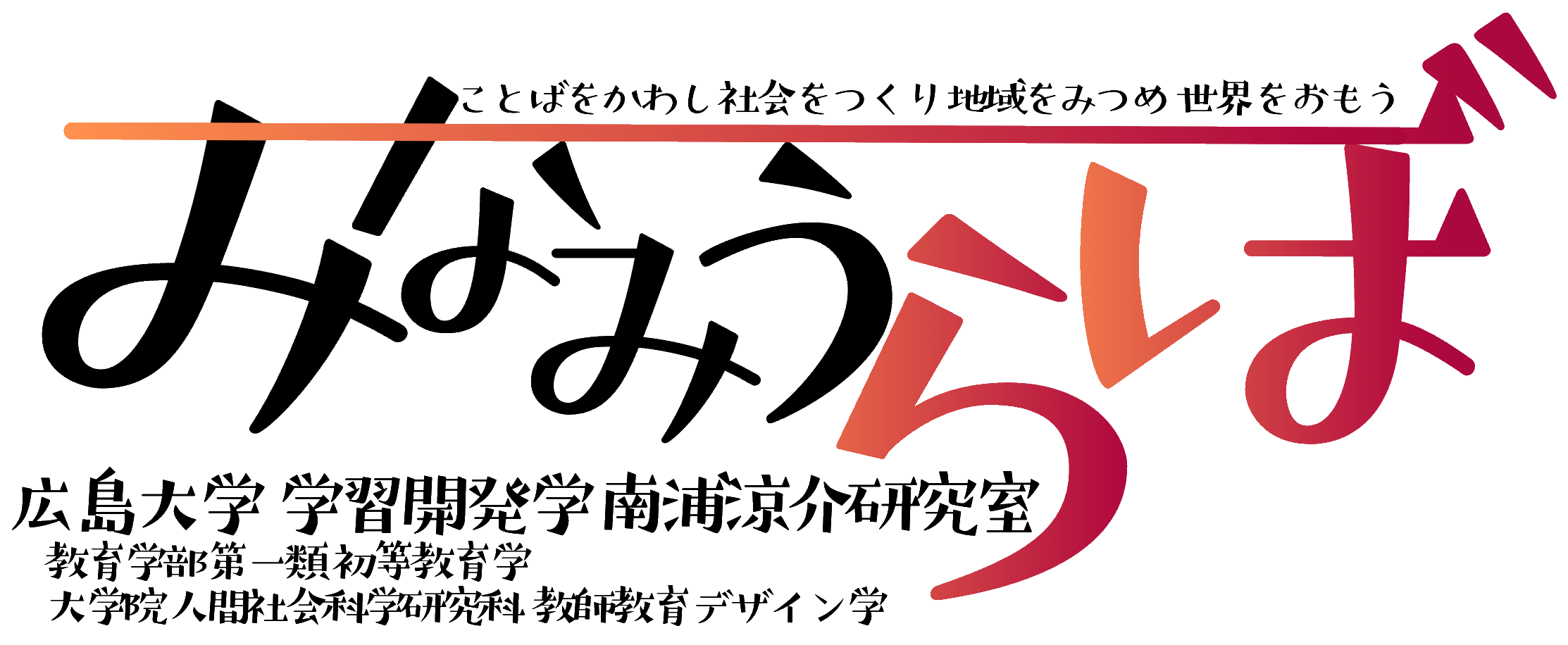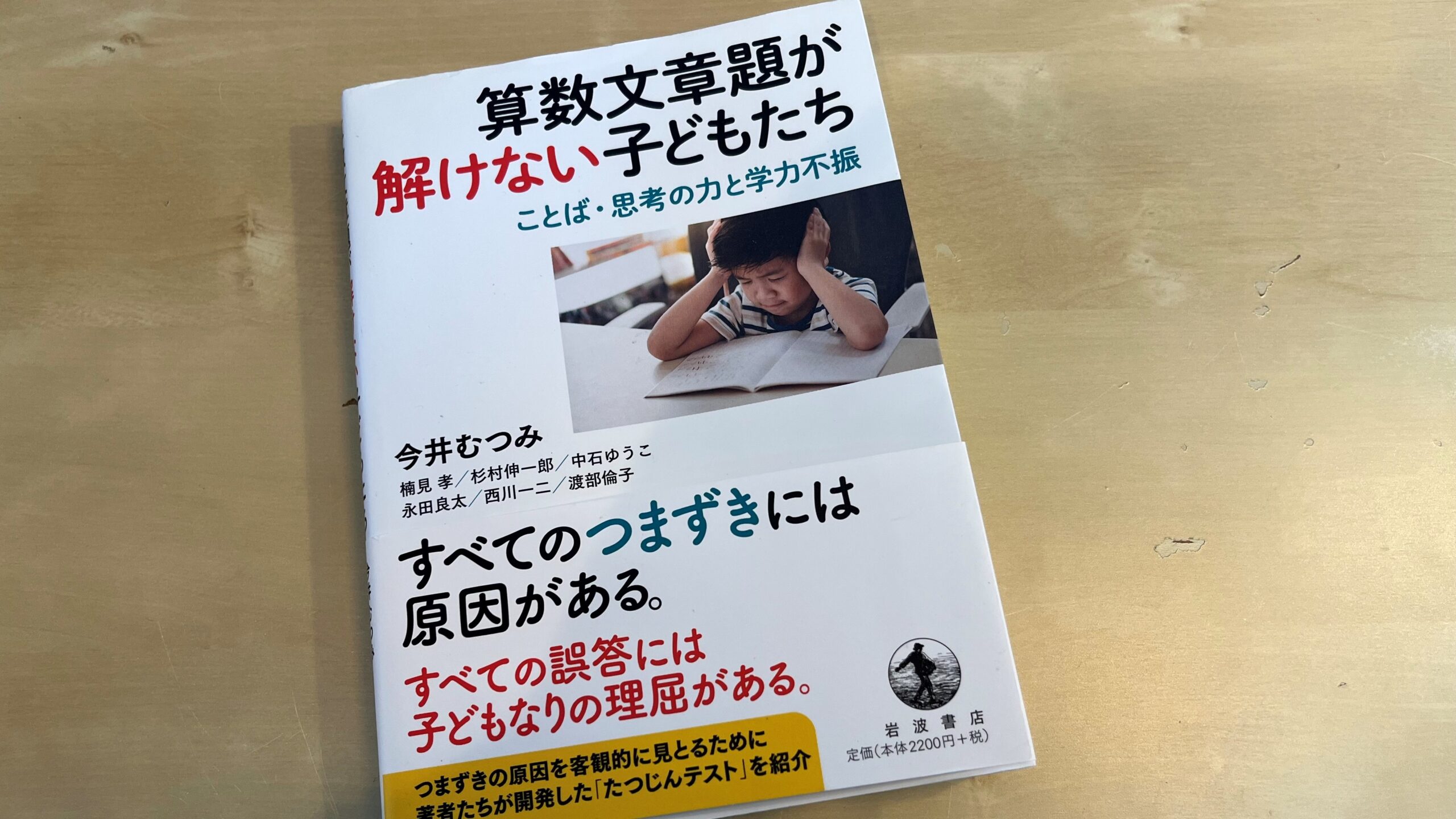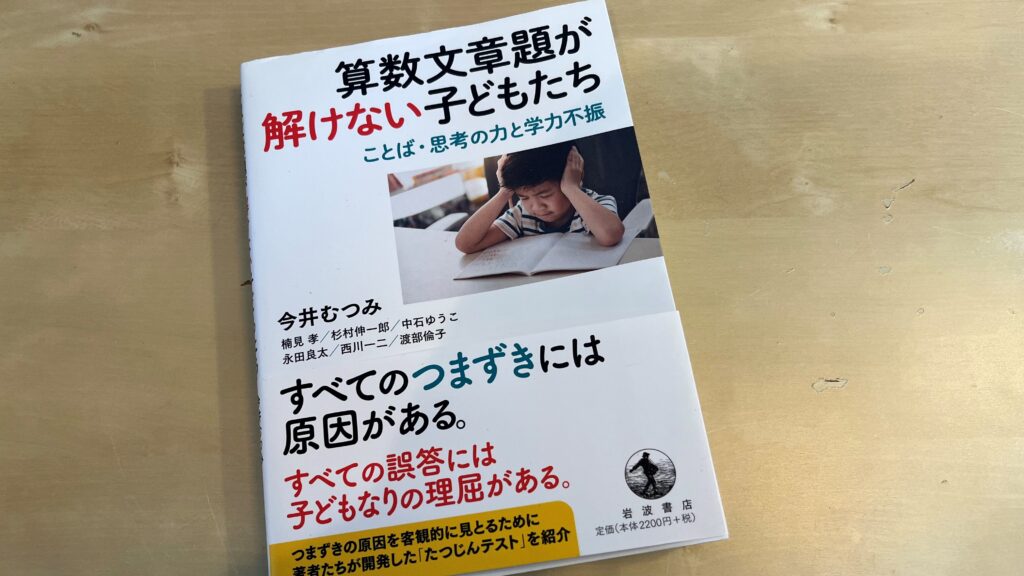
今井むつみ・楠見孝・杉村伸一郎・中石ゆうこ・永田良太・西川一二・渡部倫子(2022)『算数文章題が解けない子どもたち―ことば・思考の力と学力不振』岩波書店
「ホンモノの力を探る」ことをめざした「たつじんテスト」の面白さ
一見して「売れるのだろうな」という直感。算数という「学力」を端的にうつしとるイメージを持つ教科を対象にして,さらに「文章題」をキーワードにすることで,そこに「言葉」と「認知」という,言語的心理的な視角を出しながら「子どもの頭の中がどうなっているのかを知りたい」「学力不振児の頭の中を理解したい」という教師や教育支援者の心をくすぐるものになっている。その意味で編纂の巧みさも感じられる。
内容はそうした読者の心のくすぐりをある意味で反する形で手堅い印象。筆者らの「従来の算数のテストは『ほんものの学力』を把握するものになっているのか」という問題意識から出発し,算数の生きた知識・使える知識を把握する試みになっている。そしてそこから,子どもたちの推論や認知過程の「つまずき」を把握する。
またそれだけでなく「根本的な問題は,子どもたちが算数の文章題を自分にとって解く意味があることだとは思っていないので,数字を使って思いつく演算をし,答えが出せればよいと思っていること,つまり,算数の問題,とくに文章題に対して持っている認識なのではないかと思う」(p.42)に象徴されるように,子どもの側からの算数教育の解釈(図らずも獲得してしまったヒドゥン・カリキュラム)への示唆にもつながっているところ。こうしたことは,教科教育学への示唆としてもおもしろいところだろうと思う。
ただし,算数/数学科教育学・教育方法学の視点から見たときに,算数の学力論をどう捉えるのか,それは推論や認知過程,あるいは数理概念の形成のみで捉えていくものなのか。数学的なものと認知的なものと実用的なものの間で,テストが根ざす学力像や目的論の妥当性はもう少し整理される必要があるかもしれない。
「データを駆動させて教育をつくる」風潮の中における本書の位置
こうした面白さの一方で,この本が「売れそうだ」と思ってしまう,教育をめぐる社会的状況を考えてみると,本をめぐる社会という点で危惧もある。学力不振や学力向上をめぐる日本の教育政策は,さまざまな社会の風潮や説明責任・応答責任を求められる中で「データを駆動させて教育をつくる」という形がますます求められ,強くなってきている。そうした中での本書の位置づけも確認してみたい。
本書ではつぶさに描かれる子どもの解答結果が,本書のタイトル通り「算数」「言葉」「認知」というキーワードで表される。亘理陽一さんが書評でもすでに述べているが,そうした認知主義的(亘理のいう「ピアジェシャン的」)に理解されていくことはには危惧も感じる。(それは筆者らの目的の範疇外なのかも知れないが)
認知心理的な発想と実践の関係はすでに90年代後半から日本でも相当に批判的な蓄積もなされてきているが,一方で世間的には「認知と教育」は関心的にも過度に単純化されて結びつきやすい。(例えば日本語教育でもSLAと教育実践の関係をめぐって論文で見られるが,研究の世界でもときに「心理がわかれば実践ができる」のように単純に結びつけられる)
本来,その結果の背景やその結果に対抗していく実践は社会文化的な視点がかなり重要となる(上のp.42の引用も,まさにそうした視点である)。もちろん,筆者らはそこに「統計は目の前のひとりの子どもの特徴の理解には役に立たない」(p.170)など,再三にわたってそうした発想に注意喚起をしている。
が,エビデンスと教育政策が(単純に)密接につながって進みがちな現在,こうした本書の「売れ具合」と「インパクト」の方向性が筆者らの思惑と外れて受け止められていかないかは気になるところ。
ただし,筆者らは本来は「公教育の目標はすべての子どもが落ちこぼれることなく,生き生きと学ぶことができるような環境と支援を提供することであるはずだ。そうであるならば,現行の学習指導要領のどこに子どもがつまずくのか,それはなぜなのかを知ることは,教育の施策に欠かせない視点のはず」(p.4)と宣言するように,「ほんものの力を把握するテスト」を開発することを通して,「よりよいエビデンスで政策決定をすること」を促そうとしている。これは,よく見られる「EBE(エビデンスに基づく教育)」をめぐる批判が,そうしたエビデンス主義そのものに目線が向けられることに対して,エビデンスの内実を検討し,よりよいものを計上していこうとするところに力点を置くという点でも興味深い点だ。
そうした企図が,かつて「全ての子どもの落ちこぼれをなくす」からはじまって結果的にテスト主義に陥ったアメリカのNCLB法のようになっていきかねない日本の教育政策の中であることに,筆者らがどこまで自覚的であるのか,あるいは自覚的であっても安易なdata drivenの教育政策の中に飲み込まれていくのか,あるいはそうした潮流における一つのくびきとなりうるのか。広島県教育委員会や福山市教育委員会がどのようなインパクトを持ってこれを受け止めているのかという点も含めて(こうした行政側の受け止めについては言及されていない),目を追っていきたいところだ。
外国につながる子どもたちの教育と,エビデンスと政策をめぐる本書の展開の期待
また,筆者らの半数は日本語教育の関係者であるが,日本語教育の研究は,教育学的に見ると,系譜的にも「エビデンスと教育」が密接にかかわり合う世界にある。そうした中で,例えば「外国につながる子どもたち」の教育などにはどのように利活用可能なのかを考えてみるのは重要だろう。
「日本語の取り出し教室」は「エビデンスと教育政策」のエアポケットにあって一見牧歌的に見えるが,実はその教室や子どもをめぐる評価には「エビデンス」の捉え方をめぐる教師や学校,行政の誤謬がかなり存在する。この点は,ピアジェ的な視点だけでは解決ができない(が,そうした研究も言説もけっこう多い)。ここにどう刺さっていくか,興味深い。