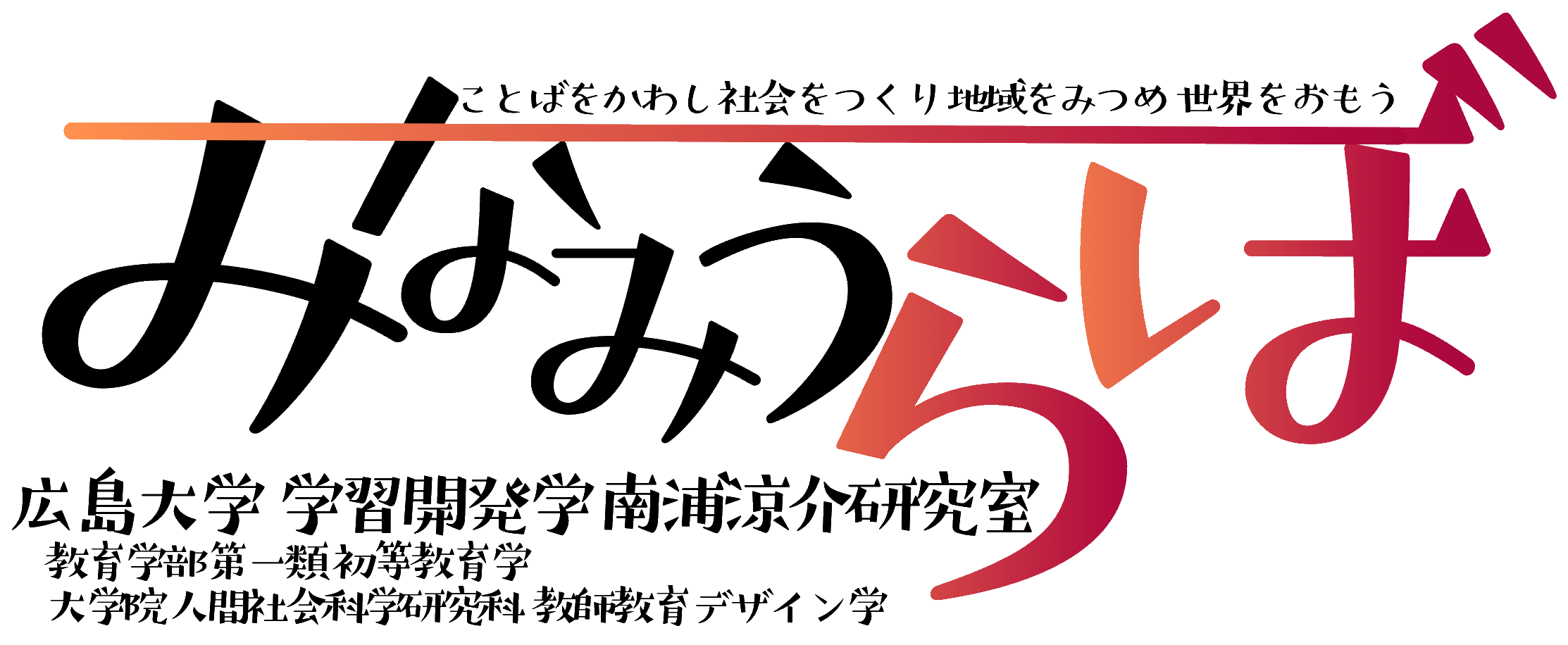正月にアップルの『カリキュラム・ポリティックス』を読んだので,その前に訳されているアップルの基礎的な文献として『教育幻想とカリキュラム』。
もともと,アップルを手に取ったのは,外国人児童生徒とカリキュラムの関係性を捉えるためにその基礎文献としてだった。
『教育幻想とカリキュラム』自体は日本語版が1986年,原著の “Ideology and curriculum” も1979年発行で,すでに内容としてはいろいろなところで言及されているので,わざわざ解説するのはおこがましい。
アップルがこの後連綿と検討していくことは恐らくこの時点である程度でている。なので,あえて,もともとの自分自身の研究に近づけて,外国につながる子どもたちをめぐる教育との関係で捉えてみたい。
例えばアップルが言う「学校で教えられる知識は社会の支配層によって選ばれ,公式化される」は,外国につながる子どもたちがよく問題にされる「学習言語能力がない」言説を思い浮かべてしまう。このときの「学習言語」と想定されるもの自体がそもそも学校制度と教師が前提にしている「教科書に書かれているエリート的知識とそのリテラシー」になっているわけで。
このことは英語圏の論文ではたびたび「イデオロギーとしてのリテラシー(ideological and critical perspective on literacy)」として語られている。
でも,こうしたリテラシ自体が日本ではどうも自明のこととされて問い直しが入らない。それはそのリテラシーに乗っからないと「進学やキャリアに外国につながる子どもが乗っかれない」から,だ。
しかし,そうしたこと自体をアップルはすでに批判している。「市場原理主義と教育」「技術的合理性」と教育は,教育のカリキュラムが,いわゆるイデオロギーとは言っても右派左派的なもの以上に,産業社会のニーズに合わせて設計されていくということを何度もアップルは指摘している。
「わからないことがわかるように」「できないことができるように」を自明として外国人児童生徒の教育は進むのだけれども,その「わからないことが」「できないことが」自体が,何によって,誰によってつくられ,規定されているのかをカリキュラムのつくられかたという点から考えること――。
ああそれは,2023年にカリキュラム学会でシンポジウムとして登壇したときのテーマ「ダイバーシティとカリキュラム」はまさにそれをテーマにしようとしていたのだなと,2年越しに改めて思い至る。
そうか,そうしたことをもっと前面に出しながら論じていけばよかったのだと,改めて思い至った。