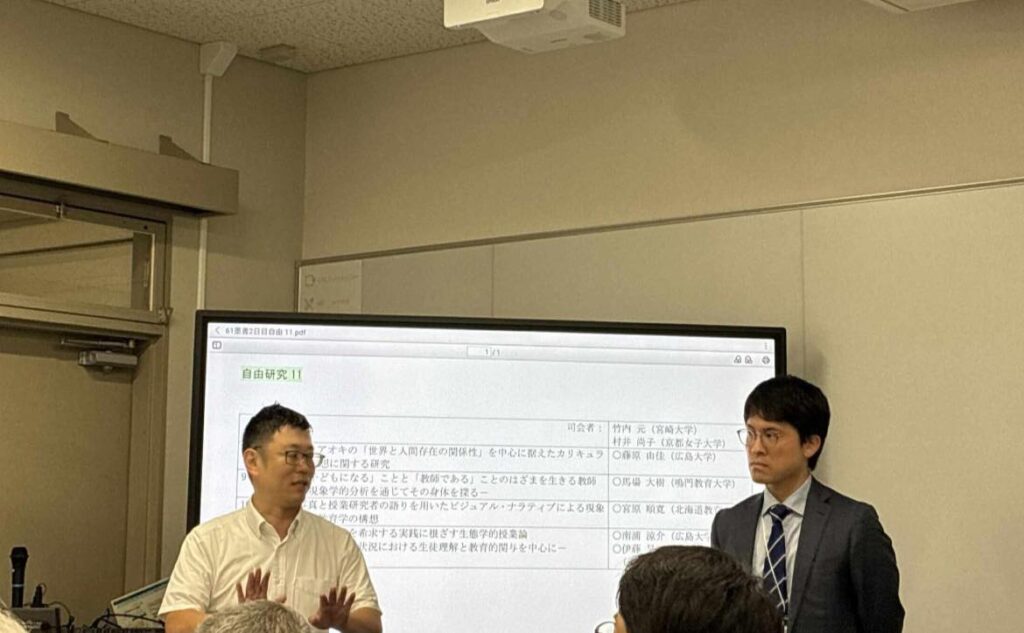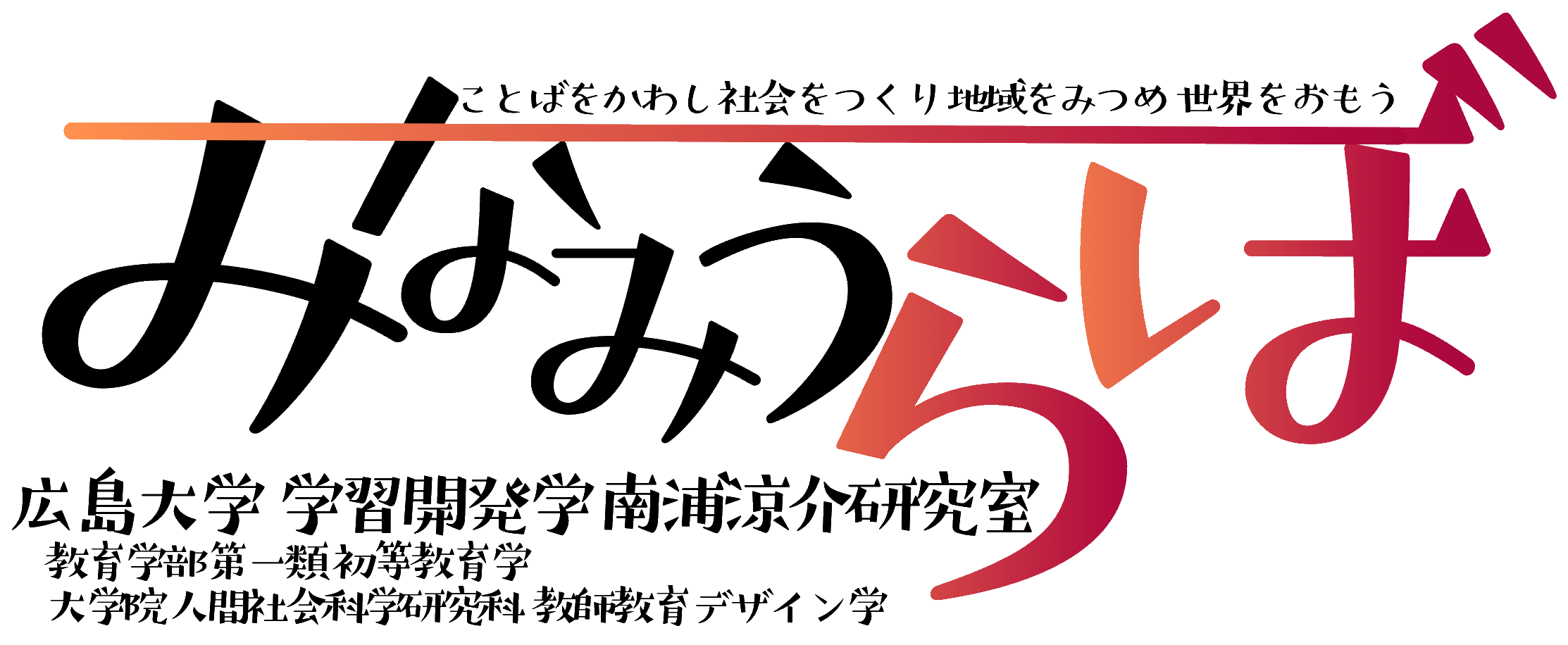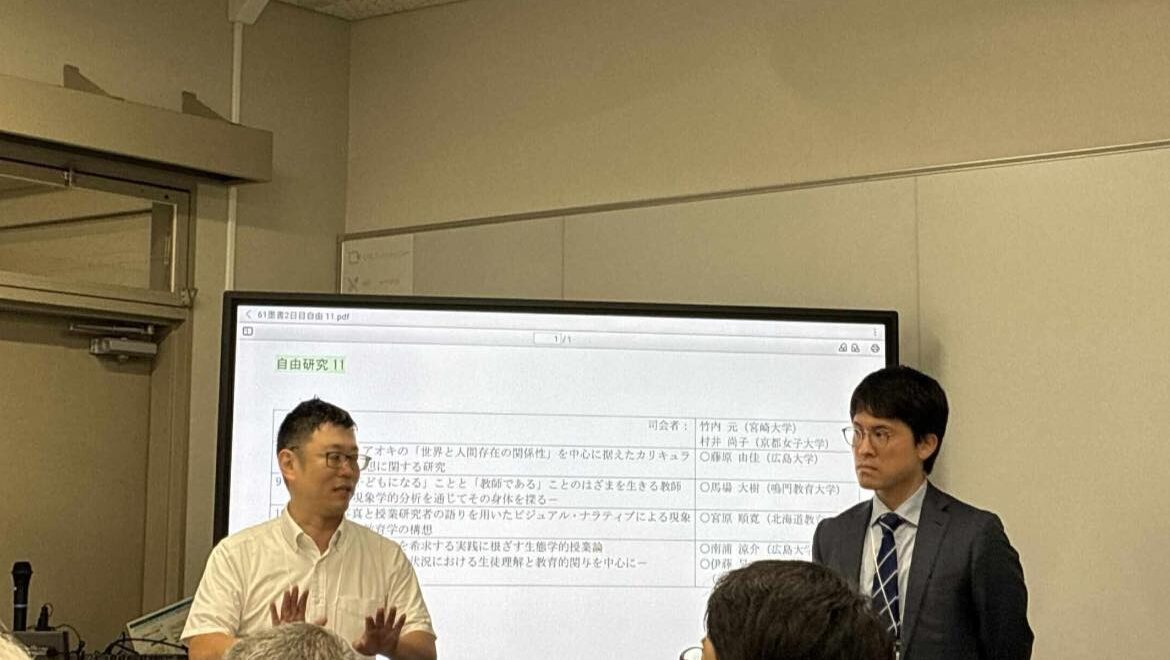日本教育方法学会で、千葉県佐倉南高校定時制の伊藤晃一さんと「包摂と挑戦を希求する実践に根ざす生態学的授業論-多様な学校状況における生徒理解と教育的関与を中心に-」を発表してきました。(科研の石田喜美さん、小栁亜季さん、中川祐治さんとの共同プロジェクトのひとつです)
多様性の包摂と言えば「二階建て」(通常のクラスとピックアップのクラス)の議論が多い中、「一階そのもの」を考えるので、授業論そのものへの挑戦だったからか、たくさんの質問ももらえた。最後の松下先生との議論はヒリヒリするようなやりとりで「学会発表ならでは」だったと思うし、今後の課題や方向性が明確になった。馬場先生との議論はその後長く昼も続き、下の現象学的な視点と伝統的な教育学的なものの接点を考える勇気にもなった。
また、この分科会自体、現象学や生態学の視点にあふれ、授業研究の新しい息吹も感じました。タイムテーブルを組む事務局のみなさまの力もすごい。
実は教育方法学会、なぜか僕は発表をするとめちゃくちゃ緊張する。これは自分自身が分野的に新参者感覚をいつも持っているからなのと、命題について最終的には「自分もわからない」ということと、その崖っぷちに立つ中で言葉を発する感覚だからかな。
決してアウェーではなくて、友人もたくさんいるんだけど、新参者感覚。
40代も半ばの中で、まだこういう感覚を持てるのは、いいな。
南浦研究室M2のHさんも「アッサンブラージュとしての日本語教室-社会との接続を生み出す教師の行為に着目して-」を発表。とても緊張していたけど、終わってみると満ち足りた顔つき(たぶん)。大学院できちんと「学会発表」ができることは本当に大切。
「緊張してがんばる姿は美しい」と同僚の先生。慢心せず、いつになってもそんな気持ちでいたいものだ。
(写真は藤本さんより。ここは「緊張と緊張の最中のひとときのころ笑 美しくなる直前)