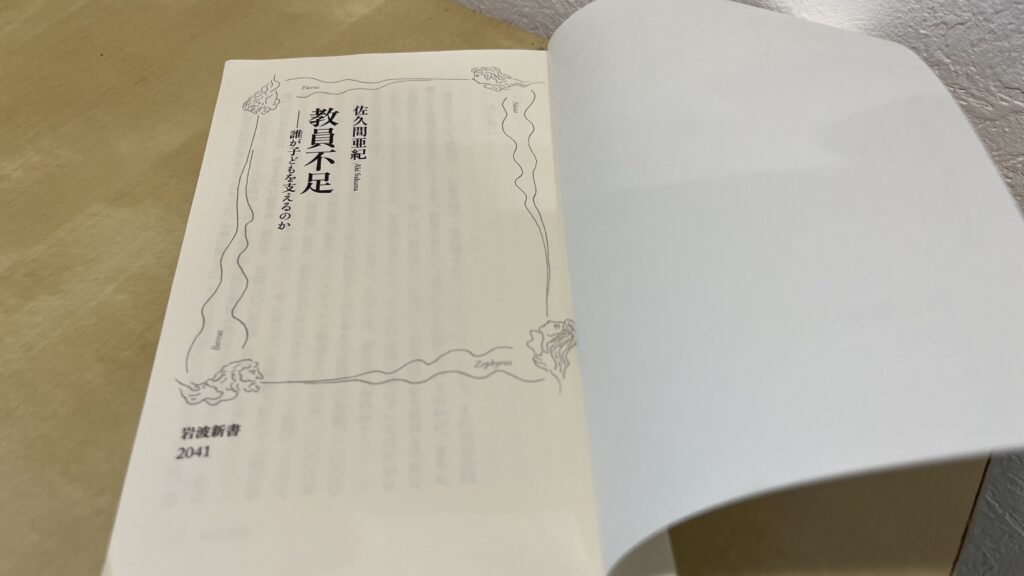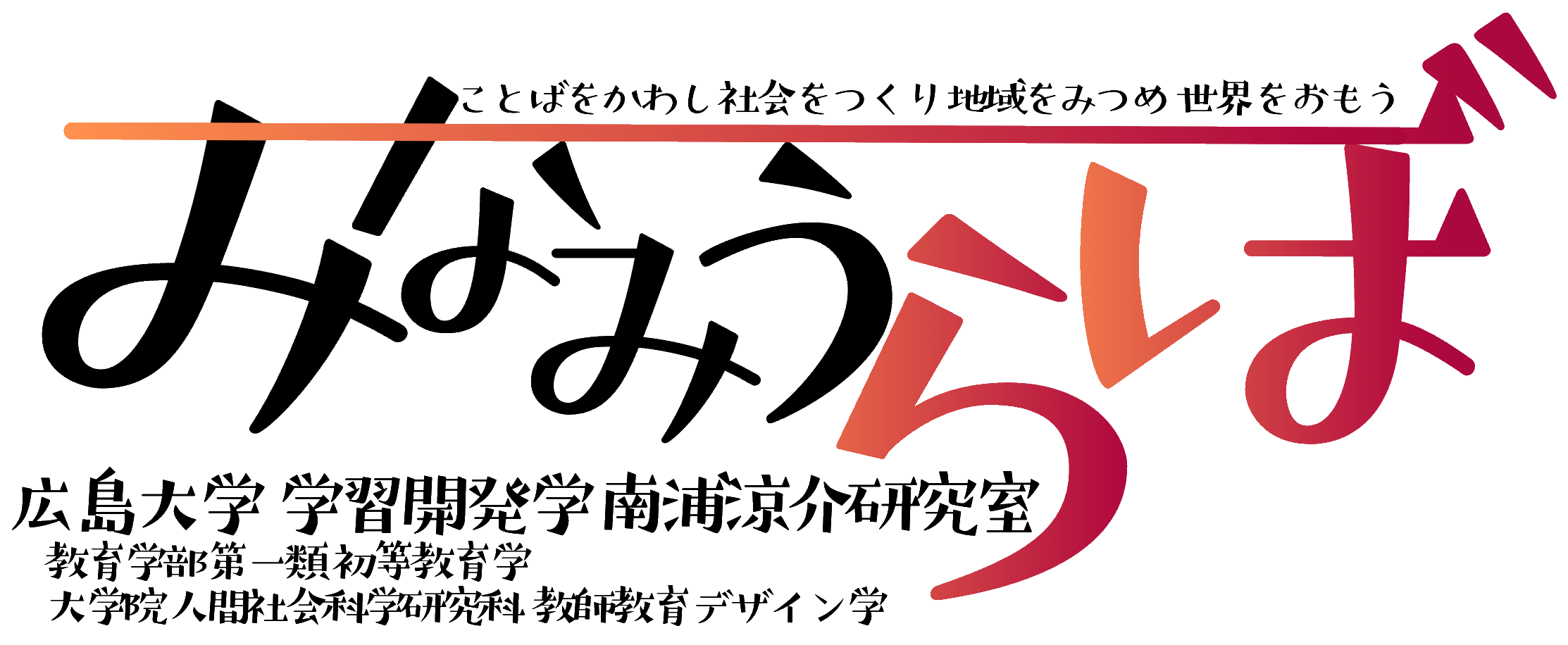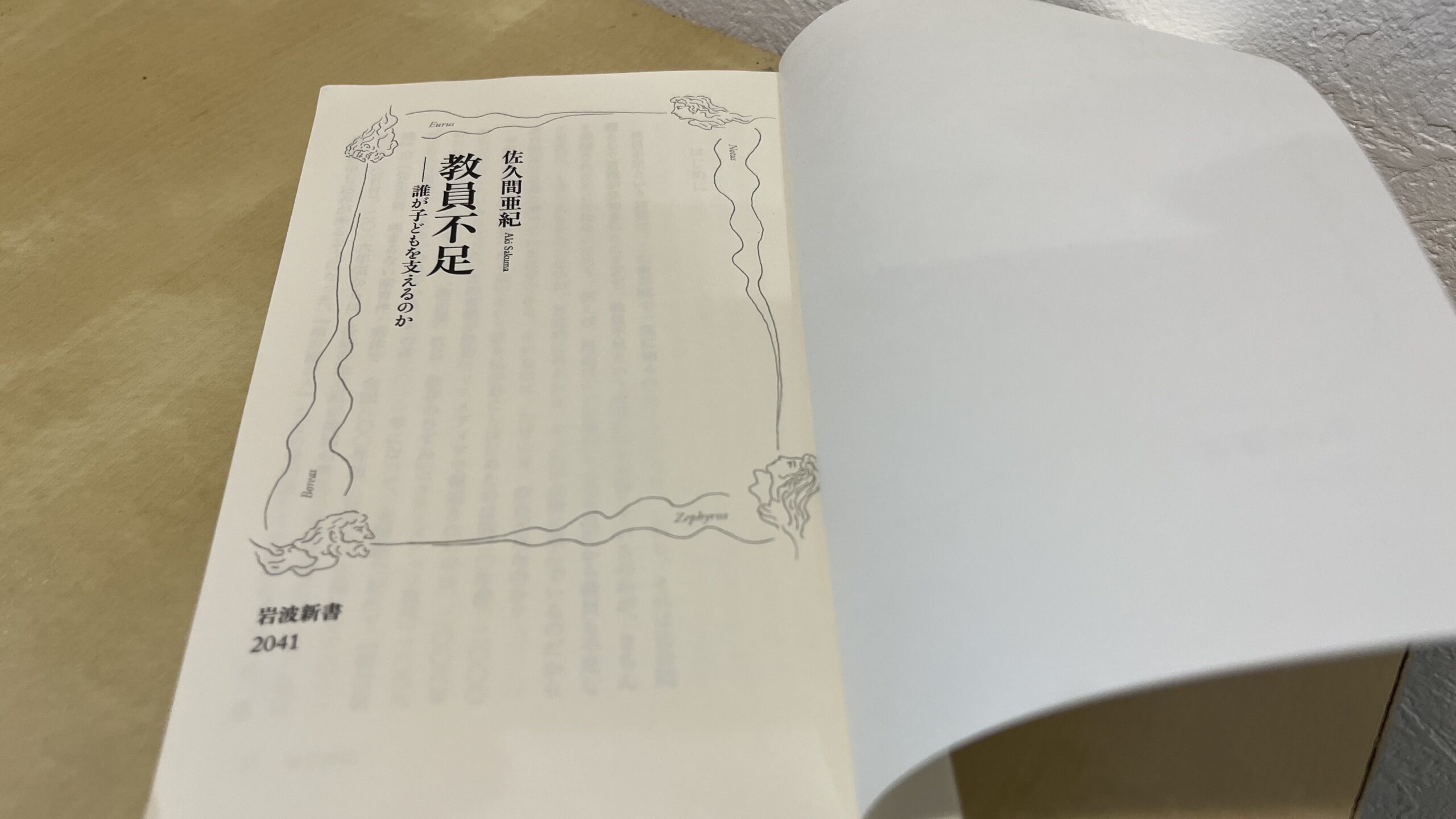いろいろなところでこの本の評判を聞く中,出張中の新幹線の中で一気読みした。
2020年代,正確に言えば2010年代後半から噴出した「教員不足」の実感は教育関係者であれば誰もが背中に冷たいものが流れる感じがすると思うのだけれども,実はそれ自体が個別の実感ではあっても「全体としてはどうなのか」「なぜそんなことが起こっているのか」が,実は見えていないのではないか,という私たちの状況がある。
この本の凄みは,冒頭のナラティブからすでにある。著者自身の周囲で「送り出した卒業生が教員になって吐露する職場では言うことができない生々しいまでの教員の状況」からスタートし,その個々人の「吐露」の背景に何が起こっているのか,後ろ側に広がる「全体」を現状と歴史から捉えていき,それをふまえて処方箋をつくろうとしている。
決してこの教員不足の状況は今に始まったことではなく,1990年代後半の橋本龍太郎政権時代のいわゆる「行革」から公務員が削減されていく世論と風潮,具体的な政策とあいまって動きはじめ,2000年代になってそれが加速していく状況が描かれる。
そうした世論と中央行政の「公務員削減」の圧の中で,自治体が苦慮しながら「教員の基礎的定数」を削減しながらそれを「講師」で賄う形で数字を工夫していく状況,しかしそれが結果的に20年後の今,どうにも動かすことができない状況をつくりあげ,1970年代まで明治以来の日本の教育の世界の「質と量と待遇の良さ」が軒並み消えていってしまう過程を描いていく。たった20年の中でのことだ。
こうした内容,多くの場合「社会学」の分野が担うことが多いのだけれども,それを,「教育史」「教師教育学」を主にやってきた佐久間氏がするというところも重要だと思う。それがあるからこの現状と歴史,さらにこの状況の行き着く先としてのアメリカの教師状況の実情を補助線にかみ合わせ,さらに教師が本来になっていた教育の内容の側面まで踏み込むことができている。
今の教員をめぐる日本の教育の世界は,もう「ある特定の分野」だけが担う状況ではにっちもさっちもいかない。いろいろな面を持った人が横断的に関わるからこそできることがある。この本もそうした仕事なのだろうと思う。
何よりも、僕自身もそうだけれど、「教員として送り出す」仕事をしながらその先でかつて初々しい学生だったあの子たちが置かれた今からスタートする筆者の「教育への愛」がこの本を作ったことが、この中身の価値を作っているように思えてならない。
教師の人も,行政の人も,政治家も,研究者も,保護者も,地域の人も,「教育」にかかわり,何が起きているのか,「教師のバトン」をめぐっていろいろなことばが交差するけれども,この本でまずは「起きていること」「起きてきたこと」「起きていくこと」「起きるかもしれない別の未来の選択」を捉えていってほしい。