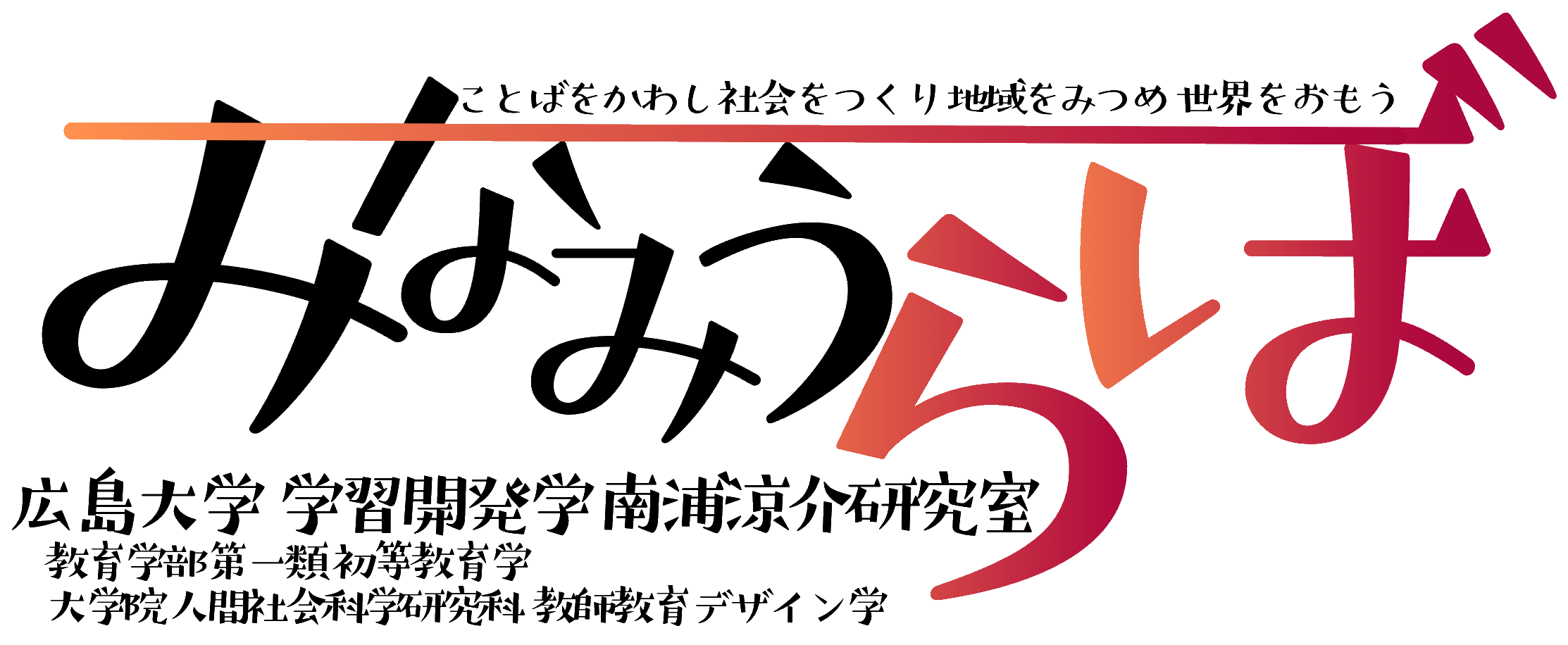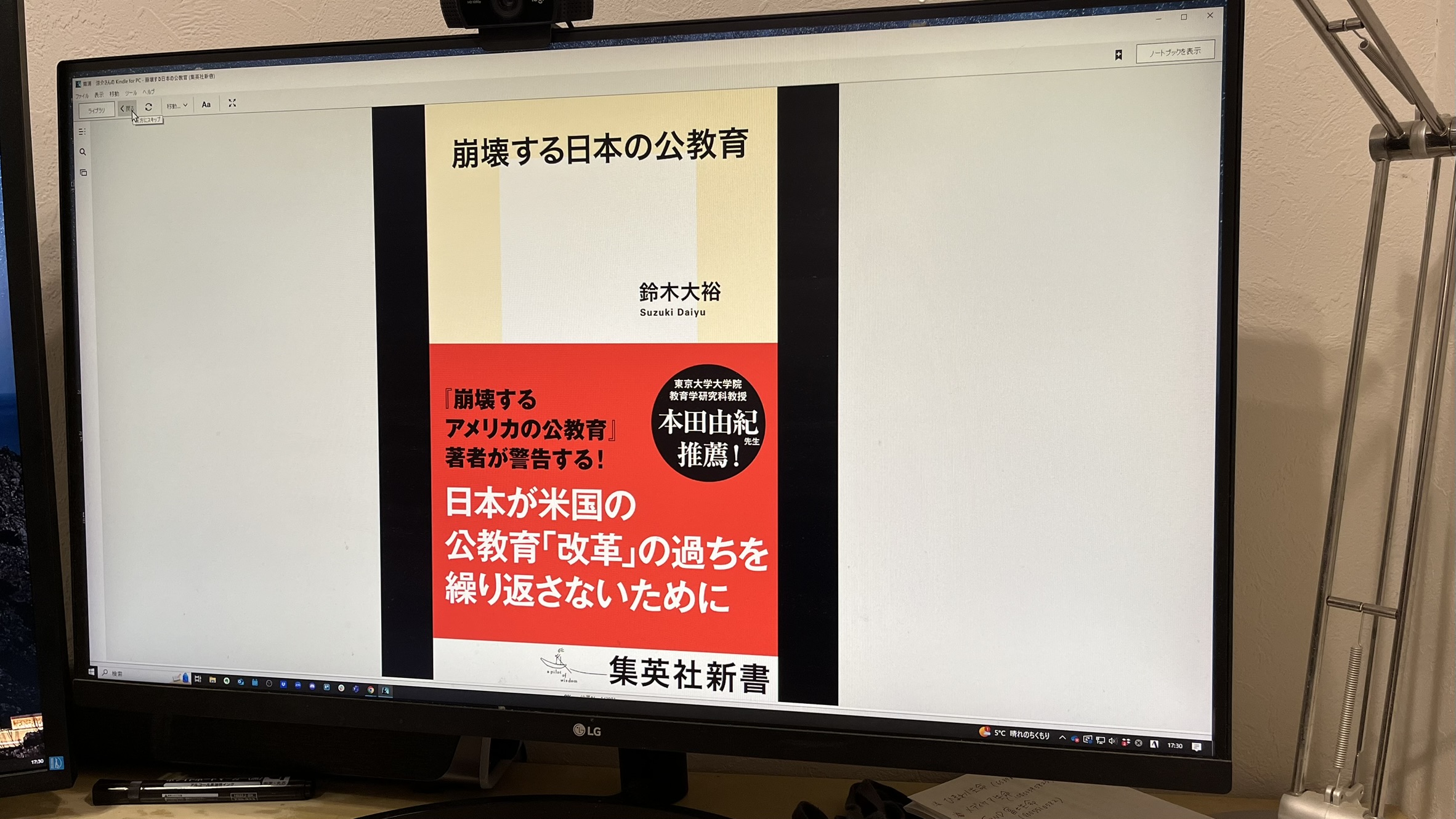教師の働き方と新自由主義的改革の問題に関するこの本の世界観。学校に市場の論理を入れ込み,教育が営利企業のような組織論理で動かされはじめ,そこに政治が入り込む。大阪市の公立学校が抱える今の状況から,自分自身が住む東広島市の「東広島スタンダード」が抱える問題まで,妙に身近な世界が描かれていた。
じっさい,僕も,僕自身が担当している「教育と社会・制度」の授業でも取り扱うのだけど、すでに今の教員養成の学生たちは大学4年生でもストレートに行っても2002年生まれ。筆者や,あるいは僕らの世代が言うところの「これが起こる前」(新自由主義・新公共管理的な学校の前の時代)の学校の世界をそもそも人生として知らないということをよく目の当たりにする。生まれながらにして,「ゴール」と「成果」の世界にどっぷりと浸かり,そしてその世界のまずまずの成功者として西日本のそこそこの大学教員養成課程(前任校は東日本のそれ)にやってきているのだ。
僕自身が1998年大学入学で,卒業が2002年3月。その後タイを経ていても日本の学校現場に直接「先生」になりはじめた時期はちょうど小泉改革のころで,学校にもそろそろ「今」の時代がやってきていたけれど,まだまだのんびりしたムードがあった。
お世話になった校長先生は本当かどうかはわからないけれど,「今日も教育委員会が来たけれど玄関で追っ払ってやったわ!」と豪語していた笑。同僚の先生たちは組合活動も熱心だったし,運動会の後の飲み会のあとは謎にみんなdeサウナだった。でもそれはもう20年も昔のことで,今の学生には全くピンとこない世界観。世代としても時代としても。
希望があるとすれば,そんな時代と世代であっても,ある種「官僚制」の時代の学校がギリギリ持っていたサラリーマン教師ではない時代の「教師像」に人は憧れて教師を志す点は変わらない。この点は大事だ。
ただ,残念ながら時代はその素朴な志を,描いた夢通りには進ませてくれない。私たちが行こうとする「学校という組織」は,どういう社会と制度の中にあるといいのか。その方向性の形にゆさぶられながら,「単に授業が巧くなれば,子どもの気持ちがわかるようになれば」という個の教師の成長像にだけとらわれない目線を,学生たちにももってほしい。そうでないと,この本の言うとおり「私が教職を去るのではない。『教師』というしごとが私から去っていったのだ」(p.180)の感覚にいとも簡単に教師は巻きこまれていってしまうので…。
(前半はとても面白かったのだけれど,後半は雑誌の記事になったものを切り貼りした観が強く,筋は通っているものの構成はやや残念。そこがいたしかゆし)