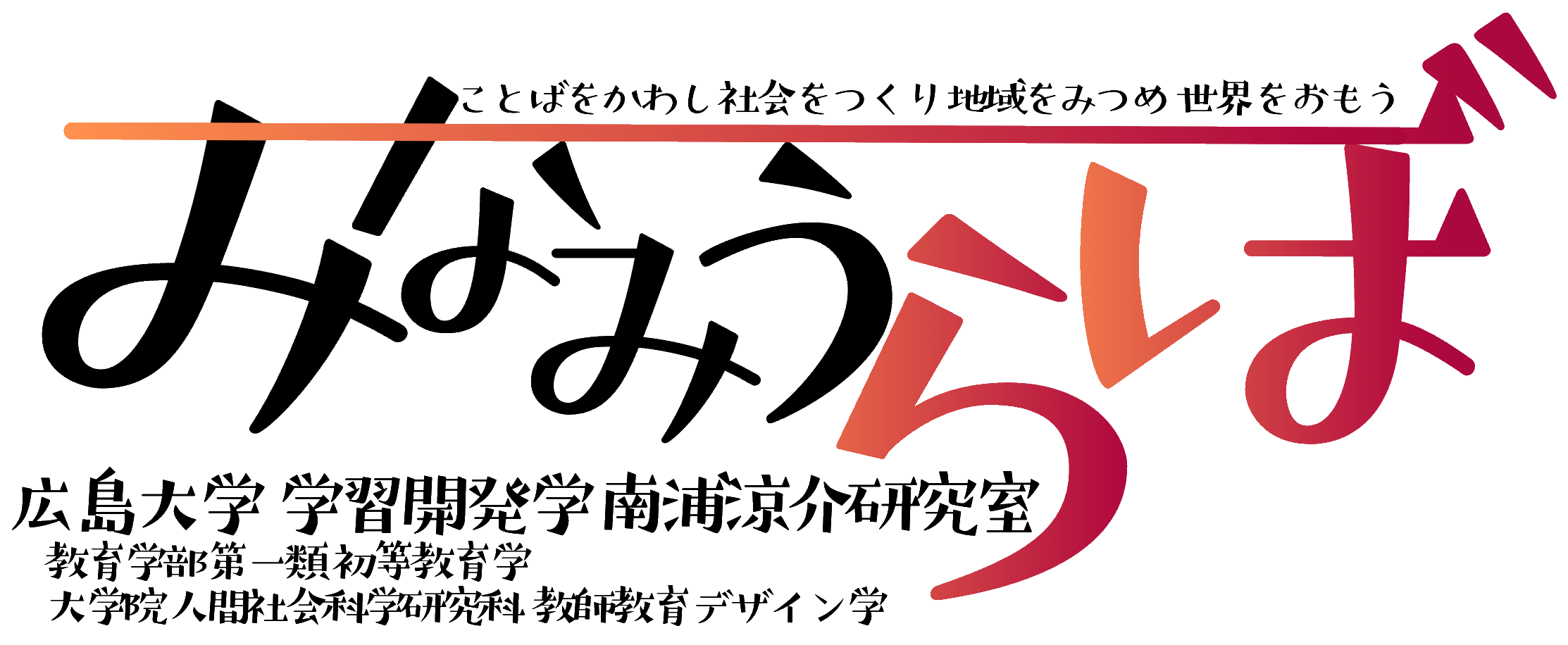試みで広島大学の学習開発学の大学院教育学系合同読書会を週1でしています。
とかく教育学は○○教育学という名の下にディシプリンもバラバラになりやすく,結果的に「学習開発学」の中でもゼミがバラバラになりやすいのですが,幅広さは可能性でもあります。実際,うちのスタッフも教育史・教育哲学(山内),教育工学・教育経営学(米沢),教育方法学・外国人児童生徒教育(南浦)と幅広い。これを活かして,『教育学年報11 ―教育研究の新章―』(2019)をみんなで読む会をはじめました。
『教育学年報』11巻は,2000年代初頭から2019年まで,それぞれの「○○教育学」の中でどのように論が展開していったのかをレビューし,現在の教育学の俯瞰的視点と論点を得るにはとてもいい。ということで,今日は「教育哲学」(下司晶, 2019)のレビュー章。
とくに今日中心的な話題になった1つが,教育の目的論と可能論。つまり,教育は教える側の目的や意図があり,それを重視していく必要があるという発想(目的論)と,教育は子どもの成長の可能性を支えることに意味があり,それを重視していくという発想(可能論)のどちらに立つべきかということでした。
こうした目的論と可能論の問題は結構根深くあります。ディスカッションは歴史的展開の上で整理をしながら,19世紀まで中心であった「目的論」中心の世界が,近代社会に入って「可能論」の芽生えがあり,それが20世紀に子ども中心主義として芽生えたこと。日本ではとくに,「戦争」の時代への反省から戦後教育学の中で可能論の側面が開いていったことに整理していきました。
ところが,可能論の発想にも実は問題があり,それが「『近代の正統的な教育思想が信奉してきた<子ども尊重>の思想が浸透した』にもかかわらず『新たな非人間化』を招来した」(p.21)という「逆説」があったはどういうことかという議論に。
そこから,初等教育の教員養成の中で学生がややもすると陥りがち(これはうちの話だけではなく,どこでも起きるある種の「乗り越えていく壁」の話です!)になる「自分たちのイメージする子ども像」に合うような学習活動を作り上げてしまい,ちょっと小難しいことや知的好奇心の高い話がでると「変わった子」という扱いになってしまうこと。さらにそこに,支援論的な発想の科学がエビデンスをもってそうしたことに補強をいれてしまうこと。そういうことは案外,外国人児童生徒や特別支援を要する子どもたちの支援論の中でも見られたりすることの例が出てくるようになり,実は「可能論」という子ども中心主義の中にある「大人の都合のよい支え」の世界が見えてもきました(ここはとても面白かった)。
そうしたことから単純な目的論から可能論へということはなく,私たちは目的論を見すえる必要もあるし,とはいえそれは学習論・可能論を捨象する話でもない中で何ができるのかというものになっていきました。このあたりの教育論と学習論の違い,近代教育批判とポストモダン,解体と再構築,子どもの捉え方…の議論は非常に興味深い。
広大学習開発学は初等教育の教員養成から来た人が多く,そうした初等の子どもたちを教える教師の脈絡から近代教育批判やその議論の展開を考えることはとてもおもしろい。
往々にして,「子ども主義」になりがちな前提がある中で,その子ども主義,学習の支援論といった一見ノンポリティカルな綺麗な話が動く中で,じつはそうした発想自体が持つ矛盾や,子どもを伸ばしていこうとするときに無垢な子ども主義に立つことの欺瞞さや,しかしながらそれを必要とすること。
また,上にもありましたが,学習支援や子ども支援(含む外国人児童生徒教育)の名の下に,実は大人に都合のよい無垢な子ども像を想定し,そこにエビデンスを入れて強固にしながら,子どもを結果的にさらにドロップアウトさせて行きかねないリスクなど,とても重要な議論が今日はありました。
こうしたものを,「初等だからこそ」「学習開発学のみんなで」読むことの意味,けっこうありそうです。